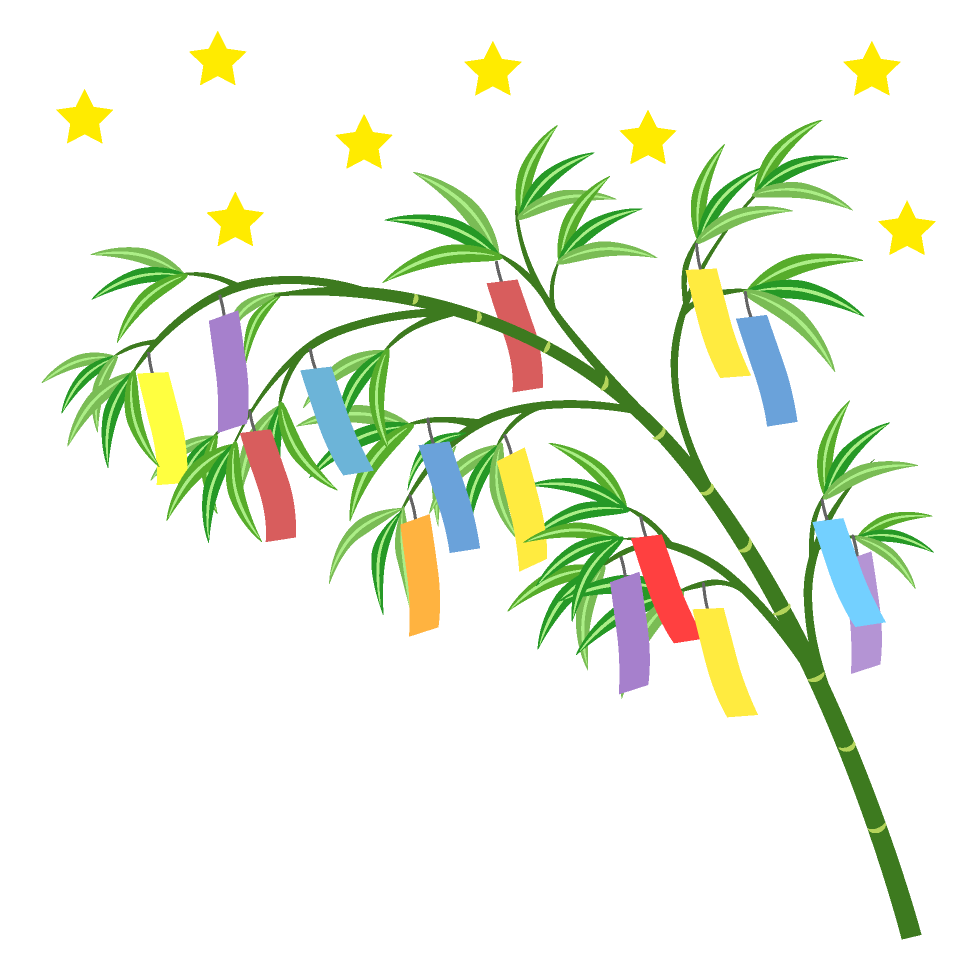今年も、七夕が近づいてきました。
笹竹に願い事を書いた短冊を飾り、夜はおり姫星とひこ星を眺め…。
最近では、そうゆう事もしなくなってしまったな…。
五節句のうちの一つである七夕。
もう少し、知っておきたい。そして、この七夕という日がどうゆう日のなのか知ったうえで、その日を迎えると、もう少し違った過ごし方が出来るのではないか。
という事で、七夕についてです。
七夕
「たなばた」、五節句で言えば「しちせき」ですね。
七夕は、五節句の一つとなります。
この日は、星祭りと言われ、旧暦の7月7日が対象となります。
そしてこの七夕は、五節句のうちの一つであり、神事を執り行う日となります。
しかし、日本の祝日法には含まれていないため、祝日とはなりません。
この旧暦の7月7日。2020年の新暦では、8月25日となります。
七夕は、7月7日までには笹竹に短冊を付け、7月7日の夜の空を眺めたりしますよね。
本来は、6日の夜の空を眺め、翌朝には短冊を付けた笹竹を川へ流すといった流れだったそうです。
※環境への配慮より、川へ流すのはやらなくなってます。
日本には、奈良時代に伝わり、平安貴族が中国の乞巧奠をまねて梶の葉に書いたのが始まりだとか。
江戸幕府により、七夕は五節句の一つとして、式日と定められます。
大奥では、白木の台に瓜・桃・菓子などを盛りつけ、その四隅に笹竹を立てて、短冊や色紙を結び付けました。
それが、街に広がり、人々風習となっていきます。
七夕といえば、おり姫とひこ星

七夕の伝説といえば、おり姫とひこ星による恋愛の物語ですよね。
この話は、中国から伝わった説話です。乞巧奠(きこうでん)と言われてます。
この乞巧奠は、7月7日の行事であり、女性が手芸や裁縫などの上達を祈ったものとなります。
日本では、奈良時代に取り入れられ、棚機津女(たなばたつめ)の伝説などと結びつき、現在の七夕になったと言われてます。
七夕の物語と言えば、
織姫は機織りの上手な働き者で、天帝の娘でした。彦星は牛飼いの働き者でした。天帝は、この二人を夫婦にさせました。二人があまりに仲が良く、織姫は機織りを、彦星は牛飼いの仕事をしなくなったため、怒った天帝は天の川を隔てて別居させ、年に一度の7月7日だけ逢うことを許した。
という話ですね。
織姫は、おりひめ星です。織女星(しょくじょせい)として知られ、こと座のベガとなります。こと座の中で最も明るい恒星です。
彦星は、ひこ星ですね。牽牛星(けんぎゅうせい)として知られ、わし座のアルタイルとなります。わし座で最も明るい恒星です。
日本の棚機津女(たなばたつめ)の伝説とは
棚機女とは織物を作る手動の機械を扱う女性を指してました。
7月6日に水辺の機屋(はたや)にて、機を織ります。そして、織りながら、神の訪れを待ちます。
その選ばれた女性を棚機津女と呼びました。
神は、7月6日の訪れ、翌7日の夕方に変えるとされてました。
この時水辺で禊を行うと、豊穣をもたらし、厄災を持ち去るといわれてます。
七夕の過ごし方
七夕の過ごし方ですが、こんな感じのものがあります。
- 願い事を書いた短冊を、笹竹に飾る。
- 夜、星を眺める。
- そうめんを食べる。
以外に知られてない、そうめんを食べるには意味があります。
願い事を書いた短冊を、笹竹に飾る
小さいころ、よくやりました。
色紙を短冊状に切り、願い事を書き、笹竹へ紐で吊るす。
夢は追い続けないと、ですね。
他力本願のような気もしますが、実は自力での実現であったりもします。
願い事を書きだすって、自分自身に打ち勝つ「克己」につながると思います。
しかも、みんなが見える様にすることは、さらに強い力が働くのではないでしょうか。
そう考えると、やってみる価値ありですね。
また、笹には、邪気や病魔を祓うと言われます。
邪気や病魔を祓うためというのも、ありですね。
夜、星を眺める
おとひめ星(ベガ)とひこ星(アルタイル)、こと座とわし座、そして天の川を眺め、ゆっくりと過ごすのものいいですね。
7月7日は、梅雨の時期のため、タイミングが必要ですが、この日はきれいな空を見たいです。
毎日は空を眺める事をしてませんが、少し心の余裕を持つのもありなのかと、思いました。
ちなみに、天の川は英語で「Milky Way」(ミルクの道)ですね。
そうめんを食べる
古代の中国にて、帝の子が7月7日に熱病で亡くなり、その子が霊鬼神となって熱病を流行らせました。
生前、その子の好物の索餅(さくべい)をお供えしたところ、熱病がおさまったことより、索餅を食べる様になったと言われてます。
索餅は、編み上げた小麦粉のお菓子のようなもので、同じ小麦粉から作る「そうめん」への変わっていきます。
そうめんを食べるというのは、「無病息災で過ごせる」という健康祈願となります。
今年も、そうめん食べて、無病息災ですね。